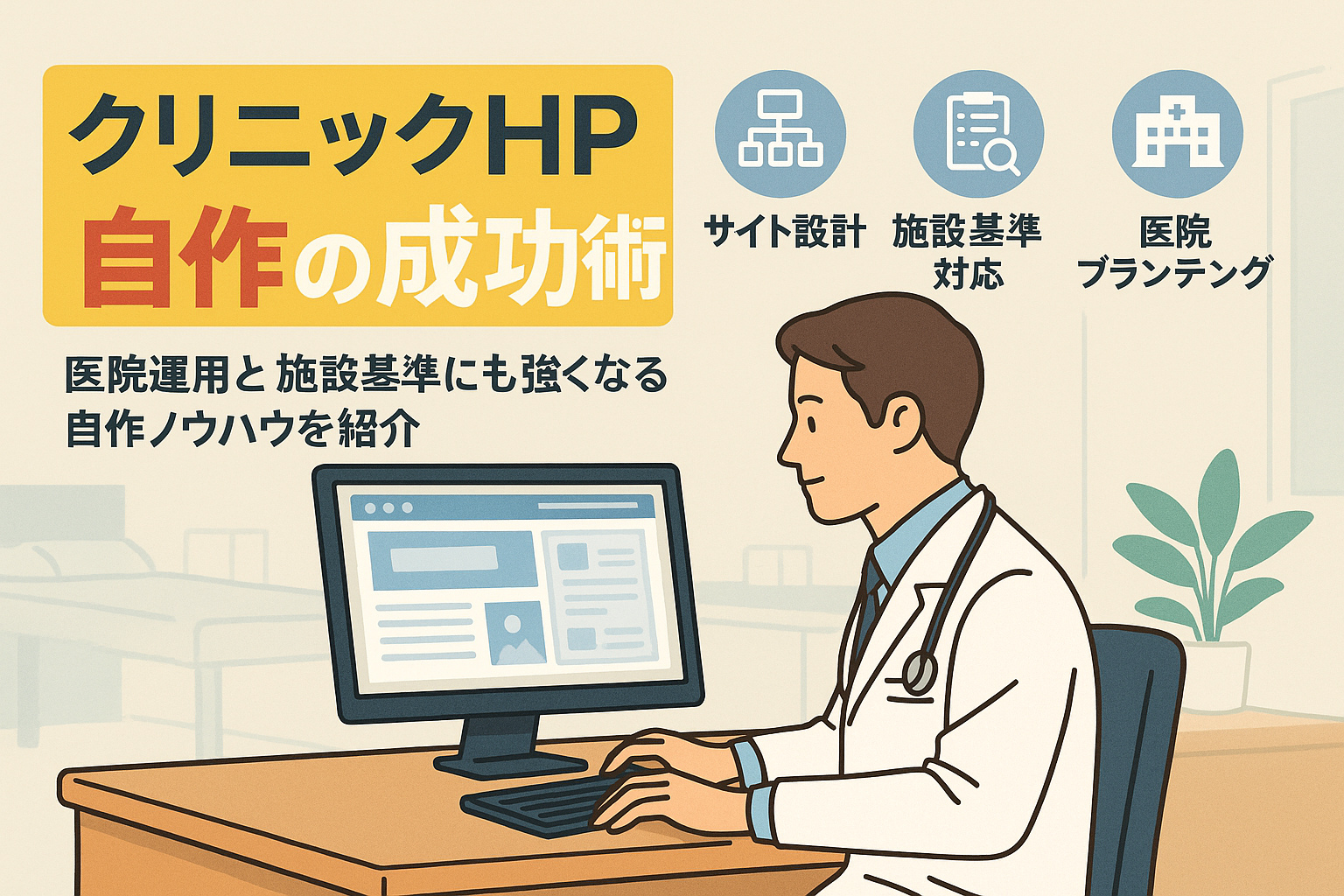
あなたのクリニックのホームページ、本当に“患者に選ばれる設計”になっていますか?
「とりあえず外注に任せた」「数年前に作ったきりで更新できていない」「スマホで見ると文字が小さい」──こうした悩みを抱える医療機関は少なくありません。今、そんな現場の中で注目されているのが、開業医や医院スタッフによる“自作ホームページ”という選択肢です。
かつてはWeb制作といえば高額な外注が前提でした。しかし、現在はペライチやSTUDIO、WordPressなど、医療機関向けのテンプレートや予約連携システムを備えたツールが充実し、専門知識がなくても費用を抑えて本格的なサイトが作れる時代へと移行しています。実際に、自作でサイトを構築したクリニックが、外注に負けない集患効果を上げている事例も増えています。
この記事では、「そもそも自作は可能なのか?」「どのツールを選ぶべきか?」「どこまで院内掲示を反映すれば法令に準拠できるか?」といった疑問に対し、具体的なツール比較・掲載必須項目・SEOとガイドライン対策を含めた戦略的な情報設計のポイントを網羅的に解説します。
本記事を読めば、クリニックの診療方針や強みを正しく伝え、患者に信頼されるホームページを自分で育てていくための“本当に必要な考え方”と“具体的な手段”が手に入ります。まずは、自院にとってベストなWeb運用のスタートラインを、ここから一緒に探っていきましょう。
医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgritsは、クリニックのホームページ制作を通じて集患をサポートします。患者様に選ばれるデザインと情報設計により、クリニックの魅力を最大限に引き出し、診療予約の増加を目指します。漫画や動画、SNS活用も取り入れ、オンラインでの集客力を高めます。各クリニックの特色に合わせたホームページ制作で、患者様との信頼関係を構築し、効果的な集患を実現します。

| 医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits | |
|---|---|
| 住所 | 〒550-0013大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F |
| 電話 | 06-4393-8493 |
クリニックのホームページを自作する前に考えるべき基本(失敗回避のスタートライン)
クリニックのホームページ自作で集患とコストを両立する方法
「クリニック ホームページ 自作」というキーワードを検索するユーザーの多くは、開業準備中の医師や既にクリニックを経営しているがWeb集患に課題を感じている方です。特に、コスト削減や集患強化、スピーディな開設を目的とした「自作ニーズ」が高まっており、制作会社に丸投げする時代から、必要な知識だけを取り入れて自ら制作・運用したいという層が増えています。
このキーワードに込められた検索意図は、単なる制作手順の習得ではなく、「自院に最適なサイトを、できる限り安く・簡単に・早く公開したい」という欲求にあります。そのため、ターゲット層は大きく以下の3つに分類できます。
- 開業予定の医師(コスト重視型)
初期費用をできるだけ抑えつつ、最低限必要なコンテンツを備えたサイトを構築したいと考える層。WordPressやペライチ、STUDIOなどの無料・低価格ツールに関心が高いのが特徴です。 - 既存クリニックの院長(リニューアル検討層)
以前作ったホームページが古くなり、スマホ非対応・SEO効果が薄い・更新が難しいといった課題を抱えている層。自作による「運用コストの最適化」や「最新情報の即時反映」を重視します。 - 医療機関のWeb担当者やスタッフ(実務支援型)
院長の指示を受けてホームページ作成を代行する立場にある方。医療広告ガイドラインの知識や、画像・文章の著作権への配慮、予約システムとの連携など実務面での悩みを抱えています。
また、検索キーワードには「自作」という語が含まれているため、低コスト化だけでなく、「自分の手で作ることで自院の方針や診療の特徴を反映したい」という情緒的ニーズも潜んでいます。これは、テンプレートだけでは表現しきれない「人柄」「治療方針」「クリニックの空気感」を伝えるために、自ら文章や構成を考えたいという開業医ならではの欲求といえます。
このように、「クリニック ホームページ 自作」は一見シンプルな語句でありながら、コスト、スピード、表現力、法規制への対応、SEO、スマホ最適化、患者の検索行動分析など、非常に多面的な要素を内包するキーワードです。そのため、コンテンツを制作する際には、検索意図の多層構造を理解し、それぞれのターゲットに応じた「段階的な情報提供」が求められます。読者が最終的に「これなら自分でもできそうだ」と安心して行動できる導線設計が、最も重要なポイントとなります。
クリニックのホームページで失敗しないための設計3原則
ホームページを作る「目的」を明確にする
クリニックのホームページを作る理由が曖昧なまま制作を開始すると、結果的に誰にも届かない、何も伝わらないサイトになってしまいます。以下のような目的を明確にすることで、設計や掲載内容に一貫性が生まれ、SEOにも好影響を与えます。
- 初診の患者を増やしたい
- 地域名で検索されたときに上位表示させたい
- 既存患者に診療時間や予約方法を案内したい
- 採用情報を掲載したい
目的ごとに必要なページ構成は異なります。たとえば「採用」が目的であれば、求人ページ、働く環境紹介、福利厚生などの情報が重要となります。開業医や個人事業主に多い誤解が、「なんとなくあった方が良さそうだから作る」という動機です。このような姿勢はコンテンツの質に直結し、離脱率を上げてしまいます。
ターゲットとなる「患者像」を明確にする
ターゲットが明確でないホームページは、メッセージ性に欠け、ユーザーの共感を得られません。どのような診療科目を中心に据えているか、患者層は地域密着型なのか、ファミリー層・高齢者・ビジネスパーソン・乳幼児の保護者など、想定する来院者の属性に応じて構成は大きく変わります。
以下に、ターゲット別で異なる掲載すべき情報例を示します。
| ターゲット層 | 優先掲載すべき内容 |
| 高齢者層 | 診療時間のわかりやすい表示、バリアフリー情報 |
| 小児科を探す親 | 発熱外来対応、休日診療有無、予約システムの案内 |
| ビジネスマン | 昼休み診療、夜間診療の有無、駅からのアクセス情報 |
| ファミリー向け | 駐車場の有無、家族で通える診療科の記載 |
| 求人希望者(採用) | 院内写真、スタッフ構成、福利厚生、医療機器の設備紹介 |
このように、ホームページは来院者との最初の接点であり、コンテンツが合致していなければSEO以前に離脱が増えてしまいます。
どんな「情報を掲載するか」を整理しておく
クリニックのホームページに掲載すべき内容は、以下のような構成が基本です。中でも「診療内容」「医師紹介」「アクセス」は最低限必要とされる情報で、どれが欠けても信頼性が損なわれ、ユーザーの不安を招きます。
| コンテンツ項目 | 解説内容のポイント |
| トップページ | 医院名、診療科目、理念を簡潔に。目立つ予約ボタン配置 |
| 診療案内 | 診療科目ごとの詳しい説明、対象年齢や対応可能な症状など |
| 医師紹介 | 経歴、専門領域、挨拶文、顔写真(親しみを持たせる) |
| アクセス情報 | 地図、最寄駅、駐車場案内、バス停など |
| 診療時間・休診日 | 曜日別タイムテーブル、祝日の扱い |
| 予約方法(電話・Web) | 使いやすさ、初診か再診かの流れを整理 |
| お知らせ・ブログ | 休診案内、季節ごとのワクチン情報など |
| 院内紹介・設備 | 清潔感の伝わる写真、感染症対策の情報など |
とくに「診療科」ごとの特徴や、「小児科」などの専門性がある場合は特化型コンテンツにしてSEOでも優位に立てます。また、Googleビジネスプロフィールとの整合性も保つ必要があります。公開前には掲載情報の最新性、法的表現のチェック、画像の著作権なども含めて総合的に確認しましょう。
なぜ今「開業医のホームページ自作」が選ばれるのか(外注せずに集患できる時代背景)
開業医の自作ホームページが選ばれる理由と集患のコツ
開業医がホームページを自作するという選択肢は、かつてのように「専門知識がないと難しい」とされていた時代とは明らかに変わってきています。近年では、WordPressやペライチなどのノーコードツールの登場により、医療従事者でも簡単に作成・公開・運用できる環境が整っています。加えて、インターネットを活用した集患対策が当たり前となった今、自院の強みや診療方針を反映したページを自ら作成したいと考える医師が増えています。
その背景には、医療業界全体におけるIT活用の推進があります。たとえば「医療DX」などの言葉に象徴されるように、予約のオンライン化や問診のクラウド化、診療情報のデジタル連携が進む中で、ホームページもまた単なる「院の顔」ではなく、業務システムの一部としての機能を担うようになってきました。実際、多くのクリニックが「予約管理」「診療内容の告知」「感染症対応の情報提供」などを、リアルタイムで反映できるホームページを求めるようになっています。
また、外注による制作の場合、制作会社に依頼する時間ややり取りの手間、希望する内容が十分に伝わらないといったストレスを感じることもあります。これに対して、自作であれば診療内容の変更や休診日の更新などを自分のタイミングで反映できるため、スピードと柔軟性の面で圧倒的なメリットがあります。特にクリニックは患者とのコミュニケーションが重要であり、信頼性や安心感を与えるためにも、こまめな情報更新が欠かせません。
自作のもう一つの大きな利点は、集患効果の最大化です。検索エンジンに最適化された構造で記事や情報を発信すれば、地域名と診療科目で検索したユーザーの目に触れやすくなります。実際に「〇〇区 小児科」「〇〇市 内科」といった検索で上位表示されるクリニックの多くは、ホームページの構成にSEOの基本を取り入れており、更新頻度も高い傾向にあります。
さらに、自作であれば地域密着型の情報発信もスムーズに行えます。たとえば、地域イベントへの参加情報、近隣施設との連携情報、季節ごとの予防接種案内など、医療と生活をつなぐ情報を「ブログ」や「お知らせ」ページで即座に共有することで、地域に根差した信頼感を構築できます。こうした運用の柔軟さは、テンプレートやCMSの選定次第でいくらでも拡張可能です。
もちろん、制作にあたっての不安もあるでしょう。デザインセンスがない、文章がうまく書けない、スマホに対応できるか分からないなど。しかし、現在は医療機関向けに最適化されたテンプレートや、ドラッグ&ドロップで配置できる編集画面が主流で、専門知識がなくても高品質なサイトが完成します。むしろ、自分で文章を考え、写真を選び、カラーやレイアウトを決めることで「自分らしさ」を伝えるサイトになるという点で、外注よりも強みを発揮できるケースもあります。
クリニックのホームページは“自作”が有利な理由とは?
近年、医療業界では「医療DX(デジタルトランスフォーメーション)」の重要性がますます高まっており、開業医の経営スタンスにも大きな変革が求められています。厚生労働省は、診療報酬改定や施設基準において、電子カルテやオンライン資格確認の導入などを段階的に義務化しつつあり、ホームページなどのデジタル接点も「業務効率」や「患者満足度」を左右する重要要素となりました。こうした背景のなか、クリニックのホームページ制作に対するニーズも変化しつつあります。
従来、多くのクリニックではホームページ制作を制作会社に外注していました。しかし、2025年現在、制作会社に依頼する際の初期費用や月額保守料金は高騰しており、仕様の変更ごとに修正費用が発生することも少なくありません。特に中小規模の医療機関にとって、これらのコストは経営を圧迫する要因となります。加えて、外注の場合、制作から公開までに時間を要し、修正にもタイムラグが発生しがちで、柔軟な運用が難しいというデメリットもあります。
その一方で、自作によるホームページ制作のハードルは格段に下がっています。ノーコードツールやWordPressテンプレートの進化により、専門的なプログラミングスキルがなくても、スマホ対応・予約フォーム・SEO対策などを備えた機能的なサイトを構築することが可能です。また、自作であれば修正も即時対応が可能であり、院内スタッフでも簡単に更新・運用できる点が大きなメリットとなります。
さらに、医療DXの潮流の中では、デジタル施策に対する助成金制度も整備されています。例えば、地域医療連携推進法人によるIT導入支援や、自治体によるデジタル化助成などを活用すれば、ホームページの自作・運用にかかるコストを抑えることも現実的です。
以下に、外注と自作の比較をまとめます。
| 比較項目 | 外注制作 | 自作(ノーコード・WordPress等) |
| 初期費用 | 高い傾向 | 無料〜低コストで導入可能 |
| 修正対応 | 業者に依頼が必要(時間・費用が発生) | 自身またはスタッフで即時反映可能 |
| 更新頻度 | 制限あり(都度費用発生) | 高頻度の情報更新も容易 |
| デザイン自由度 | 業者依存 | テンプレートやカスタムで対応可能 |
| セキュリティ | 保守契約次第 | セキュリティ設定も自己管理が必要 |
| 管理者視点の柔軟性 | 低め | 自院の運用スタイルに合わせて調整可 |
このように、自作にはコスト削減だけでなく、運用スピードや現場の裁量という点でも明確な優位性があります。特に、診療内容の変更、医師の増減、感染症対策の情報発信など、即時性が求められる医療現場では、ホームページを自ら更新できる仕組みが経営的にも非常に合理的です。
つまり今、医療機関の情報発信において「自作ホームページ」は単なるコスト削減策ではなく、経営戦略の一環として選ばれているのです。外注制作が必ずしも悪いということではありませんが、現代のツールと医療DXの進化を味方につければ、自院の特色を最大限に伝えながら、患者との接点を高める有効な手段となることは間違いありません。
医療機関ホームページに必要な掲載内容!患者が安心する必須構成リスト
患者に信頼される医療機関ホームページに必要な情報とは?
医療機関やクリニックのホームページは、患者にとって信頼性や安心感を得るための重要な接点です。「医療機関 ホームページ」「クリニック ホームページ 内容」「安心」「記載」などのキーワードで検索するユーザーは、来院前に必要な情報を明確に把握したいと考えています。したがって、単にデザインを整えるだけでは不十分で、患者が知りたい情報を適切に掲載することが求められます。
とくに重要なのは、診療内容や医師紹介、診療時間、アクセス、予約方法といった来院の判断材料となる項目です。たとえば「内科」「小児科」「整形外科」などの診療科別にどのような症状や年齢層に対応しているのかを明示することで、ユーザーの安心感が高まります。さらに、対応可能な検査や専門性(例:糖尿病外来や禁煙外来など)についても記載されていれば、SEO効果とユーザー満足の両立が図れます。
医師紹介では、経歴・専門領域・メッセージ文・顔写真を掲載することで、初めての患者にも安心感を提供できます。写真があるだけで印象は大きく変わり、信頼性を高める効果があります。また、アクセス情報は迷わず来院できることが最優先です。最寄駅やバス停、駐車場の案内まで丁寧に記載し、スマホでも地図が確認できるようにするのが理想です。
診療時間や休診日も非常に大切な情報です。曜日別の診療時間だけでなく、祝日の取り扱いや急患対応の可否も掲載しましょう。これにより、電話での問い合わせ件数も減少し、スタッフの負担も軽減されます。
予約方法については、電話予約とWeb予約の両方に対応している場合、それぞれの流れを簡潔にまとめて記載することがポイントです。初診・再診の区別、持ち物(保険証・紹介状)なども忘れずに案内しましょう。
加えて、ブログやお知らせ欄では、休診情報やワクチン開始の案内などを定期的に発信することで、最新情報を共有でき、医院の信頼性が向上します。ここでも更新頻度が問われるため、無理なく更新できる仕組みが重要です。
以上のように、医療機関のホームページには、患者視点に立った「安心できる情報設計」が欠かせません。内容が不十分なまま公開すれば、来院機会を逃すだけでなく、信頼を損なう結果にもつながります。開業予定の医師や運用を見直したいクリニック経営者の方は、構成・掲載内容を今一度丁寧に見直すことが、成果につながる第一歩といえるでしょう。
信頼される医療サイトに必要な情報設計
診療科情報は患者が自分の症状に合うかどうかを判断する最初の手がかりになるため、ページの上部に設置し、専門分野や対応可能な検査機器、保険診療か自由診療かといった区分まで具体的に示すことが重要です。たとえば内科なら生活習慣病の管理、小児科なら予防接種のスケジュール、整形外科なら骨粗鬆症検診など、来院前に知っておくべき具体例を挙げることで検索意図に合致した情報提供ができます。
医師紹介では経歴だけでなく医療に対する姿勢や得意分野を語る短いメッセージを添えることで、患者は顔と人柄を結びつけやすくなります。写真は白衣姿だけでなく診察中や学会発表の場面など複数枚を用意し、専門性と親しみやすさの両方を伝えましょう。紹介文では学会専門医資格、研究実績、地域連携の取り組みなど客観的な事実を盛り込み、裏付けある信頼を示すことが肝要です。
アクセス案内は高齢者や初診の家族連れを想定し、駅からの徒歩時間、バス停の名前、駐車場の台数を文章で丁寧に説明します。土地勘のないユーザー向けに近隣のランドマークも併記すると道順検索の負担を減らせます。また雨天での導線や車いす利用時のスロープ設置箇所などを予め示すことでバリアフリー対応をアピールできます。スマートフォン閲覧が七割を超える状況では地図リンクの配置場所よりも読み込み速度の最適化が離脱率を左右するので、画像解像度とファイル容量にも配慮してください。
予約導線はボタンの形と色だけでなく、クリック後の画面遷移を最短二画面に収める設計が理想です。電話予約とオンライン予約の手順が混在すると迷いやすいため、初診と再診を分けた説明を用意し、予約完了後に届く確認メールの文例も掲載するとキャンセルや日時変更の手間を最小化できます。診療科別の予約枠制御が可能なシステムを導入している場合は、その機能を簡潔に紹介し患者側の安心感につなげます。
これらの必須要素を網羅した上で、お知らせ欄を使い季節性ワクチンや感染症対策の最新情報を定期配信すると、検索エンジンは更新頻度の高い信頼情報と判断し評価を高めます。さらに医療広告ガイドラインに抵触しやすい表現を事前にセルフチェックし、エビデンスのある数値や公的機関の資料へリンクを張ることで、経験と専門性に裏打ちされたホームページとして患者に安心を与えることができます。
院内掲示と連携させたホームページ運用とは?施設基準の適切な反映と記載ルール
院内掲示とホームページの連携はなぜ必要か?
院内掲示とホームページの連携は、2025年現在、クリニックや医療機関にとって避けては通れない運用テーマです。「院内掲示義務 見本」「施設基準 ホームページ掲載」「医療広告 ガイドライン」といった検索キーワードが示すように、掲載すべき情報は多岐にわたります。にもかかわらず、「何を、どこまで、どう記載すれば法令違反にならないか」という点で多くの医療機関が迷っています。
そもそも院内掲示義務は、施設基準に基づいた診療体制や届出状況を明示することで、患者に対する透明性と信頼性を担保する制度です。たとえば、「明細書の無料発行」「医療安全対策加算の届出状況」「時間外診療対応の有無」「地域包括診療加算」「特定疾患療養管理料の実施」など、外来で診療を受ける患者にとって関心が高い情報は数多くあります。
このような施設基準に関する情報を、ただ院内に掲示するだけでなく、ホームページにも正しく記載することが求められる背景には、オンライン診療の普及、検索行動の変化、スマホ最適化によるWeb接点の増加があります。つまり、患者が来院前にアクセスする媒体が物理的な掲示板からWebサイトへと変化しているのです。
このような状況で求められるホームページ対応は、「見本通りに掲載すればいい」という表面的な対応ではなく、厚生労働省の通知や保険点数の要件に準拠した表記が必要になります。特に誤りが生じやすいのが、「算定要件の未記載」「略称や専門用語の多用」「対象患者への説明不足」です。こうしたミスは広告規制違反に繋がる可能性があり、知らずに掲載していたとしても指導対象となるリスクをはらんでいます。
また、「院内掲示と異なる内容がWeb上にある」「更新日が古く、現在の届出状況と乖離している」「掲載場所が複雑で患者がたどり着けない」といった問題も実務上は頻発しています。これに対し、Google検索対策やSEOの観点では、サイトのトップページまたはアクセスが多いページ(診療案内・初診の流れ・お知らせページなど)からリンクを貼るなど、情報の発見性を高める構成が重要です。
さらに、掲載情報は「書類のスクリーンショットを貼るだけ」では不十分です。HTMLテキスト形式での記載により、Googleのクローラーが正しく読み取れる構造にすることが求められます。加えて、スマホでも文字が崩れず読みやすい表示、PDFではなく直接HTML内に記載、更新日・最終改訂日の表示も忘れてはなりません。
では、実際にどういった記載が「適切」とされているのでしょうか。医療機関が迷いやすい箇所として、「医療安全対策加算」「外来感染対策向上加算」などの加算項目があります。これらは施設基準に基づく届出状況と、それを裏付ける体制(例えば専任の医療安全管理者の設置、定期研修の実施など)まで含めて記載しなければ、患者に誤解を与える可能性があります。
医療ホームページの施設基準記載ガイド
医療機関のホームページにおいて、施設基準の記載は単なる義務ではなく、信頼構築と集患の武器になります。しかしその運用には、医療広告ガイドラインの理解と、実際の記載方法への落とし込みという二重の視点が求められます。では、実際にどのように記載すれば、ガイドライン違反を避けつつ、患者の信頼を得る表現になるのでしょうか。
まず、医療広告ガイドラインに照らした場合、「実績の誇張」「体験談の記載」「定性的表現の使用」「治療結果の保証」は禁止されています。これらは施設基準の掲載と直接的に関係ないように見えますが、誤って「安心・安全な治療を提供します」「確かな技術で丁寧に対応」などと書いてしまうと、ガイドライン違反となる恐れがあります。そのため、表現は客観性と事実に基づいたものに限定する必要があります。
例えば「当院は感染対策向上加算の施設基準を満たしています」とだけ書くのではなく、「当院では外来感染対策向上加算に係る届出を行っており、専任の感染管理担当者を配置し、職員全体への年2回の感染対策研修を実施しています」のように、根拠ある説明が有効です。これは単にルールを守るという意味だけでなく、患者にとって「この医院なら信頼できる」と思わせる明確な情報提供にもなります。
さらに、「地域包括診療加算」など地域連携に関する施設基準の場合、「他医療機関との連携」や「在宅療養支援診療所」としての機能があるかどうかも記載が必要です。ホームページの記載内容と、保険医療機関としての実態が食い違うと、保険者からの指導や監査の対象となるケースも実際に報告されています。
情報の更新についても怠ってはなりません。施設基準や医療体制は年度ごとに改定されるため、少なくとも年1回は全ページの見直しを行い、「最終更新日」を明記しておくとともに、外部からの確認も容易な構成とすることが推奨されます。
また、事例として効果的な運用を行っている医療機関では、「お知らせ」ページを活用して、厚労省の通知や地域保健所からの情報と連携し、季節性ワクチンの入荷状況、院内感染対策の強化内容などを発信しています。これにより、更新頻度の高いホームページとしてGoogleから評価されると同時に、患者にとっての「信頼性ある情報源」となり得ています。
医療機関ホームページで施設基準を正しく記載・運用することは、単に法的義務を満たすだけでなく、「情報の正確性」「更新の透明性」「患者への誠実さ」を示す重要な機会でもあります。SEO施策としても評価されやすくなるため、掲載方針と情報設計は慎重かつ戦略的に進める必要があります。患者が不安なく医療を受けられる環境を整えるためにも、今一度、ガイドライン遵守とホームページ運用のあり方を見直していきましょう。
まとめ
クリニックのホームページを自作するという選択は、今や特別なことではなくなりました。無料または低コストで始められるツールが充実し、デザイン性・機能性ともにプロ仕様に近いサイトが構築できる環境が整っています。WordPressやSTUDIO、Weveryなどを活用することで、専門知識がない開業医でも自院の特徴や診療科の強みを正しく発信することが可能です。
しかし、自作であるがゆえに注意すべき点もあります。特に重要なのは、医療広告ガイドラインと施設基準の両方に準拠した記載です。たとえば「感染対策加算の届出」「外来対応の有無」「地域包括診療加算」などは、患者にとって信頼の指標になる一方、誤記や記載漏れは広告違反や監査リスクにつながります。ホームページを“医療情報の信頼源”として機能させるためには、記載内容の正確性と更新の継続性が求められます。
また、掲載する内容はデザインよりも「正確な診療情報」「更新日が記載された施設基準」「アクセスや予約導線のわかりやすさ」が優先されます。スマートフォンからの閲覧が主流である現代では、読み込み速度や配置の工夫も集患に大きな影響を与えます。実際に自作サイトで成果を上げている医療機関では、お知らせ欄や診療案内を通じて継続的に情報発信を行い、検索順位の上昇と患者からの信頼獲得を両立しています。
初期費用や月額コストを抑えながらも、SEO効果と法令遵守を両立できるのがホームページ自作の最大のメリットです。外注に頼る前に「自分で作って運用する」選択肢を検討することで、自院の魅力をより的確に伝え、結果的に安定した集患・信頼性構築へとつなげることができます。今このタイミングで見直すことが、ホームページという「第二の受付窓口」を強化する第一歩になるはずです。
医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgritsは、クリニックのホームページ制作を通じて集患をサポートします。患者様に選ばれるデザインと情報設計により、クリニックの魅力を最大限に引き出し、診療予約の増加を目指します。漫画や動画、SNS活用も取り入れ、オンラインでの集客力を高めます。各クリニックの特色に合わせたホームページ制作で、患者様との信頼関係を構築し、効果的な集患を実現します。

| 医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits | |
|---|---|
| 住所 | 〒550-0013大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F |
| 電話 | 06-4393-8493 |
よくある質問
Q. クリニックのホームページを自作する場合、どのくらいの費用感が想定されますか?
A. ホームページを自作する場合は、選ぶツールによって費用感が異なります。無料で始められるサービスもあれば、必要に応じて有料テンプレートや機能拡張が可能なツールもあります。また、独自ドメインの取得や画像素材、フォーム機能の追加などにより費用が変動するため、自身の運用目的や必要な機能を明確にしておくことが大切です。いずれの場合も、一般的な外注と比べると費用は抑えやすく、費用対効果の高い選択肢と言えるでしょう。
Q. 自作したホームページでも、SEO対策はきちんとできますか?
A. 適切に構成されたホームページであれば、自作でもSEO効果は十分に期待できます。例えば、ページタイトルや見出しにキーワードを含める、スマホ対応を徹底する、Googleが読み取りやすいHTML構造にする、診療科や予約情報を明確に掲載するなど、基本的なSEO施策を押さえることが重要です。さらに、ブログの活用やGoogleビジネスプロフィールの最適化を通じて、地域での検索上位を狙うことも可能です。むしろ、自作だからこそ柔軟でスピーディな運用がしやすいという利点があります。
Q. 院内掲示や施設基準の内容は、どこまでホームページに掲載すればよいですか?
A. 厚生労働省の通知に基づき、正確かつ患者にとって分かりやすい形で情報を掲載することが求められます。たとえば、医療安全対策や感染対策の加算などについては、届出を行っていることだけでなく、該当する体制や実施内容についても明記しておく必要があります。ホームページ上での記載は、HTML形式で掲載し、スマホでも読みやすく構成することが理想的です。掲載情報は定期的に更新し、院内掲示と矛盾が生じないよう管理することが信頼性とSEO双方の観点からも重要です。
Q. 自作でもスマホ対応や予約システムの導入は可能ですか?
A. 現在のホームページ作成ツールは、スマホ表示に最適化されており、自作でも十分に対応可能です。スマートフォンでの表示が整っていることは、検索エンジンからの評価にも直結するため、ユーザー目線で見やすさや導線設計を意識した作りが求められます。また、予約システムについても、LINE予約やクラウド型の外部サービスと連携することで、比較的簡単に導入することができます。専門的な知識がなくても設定しやすく、来院の導線を明確にすることで集患力も高まります。
会社概要
会社名・・・医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits
所在地・・・〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F
電話番号・・・06-4393-8493
