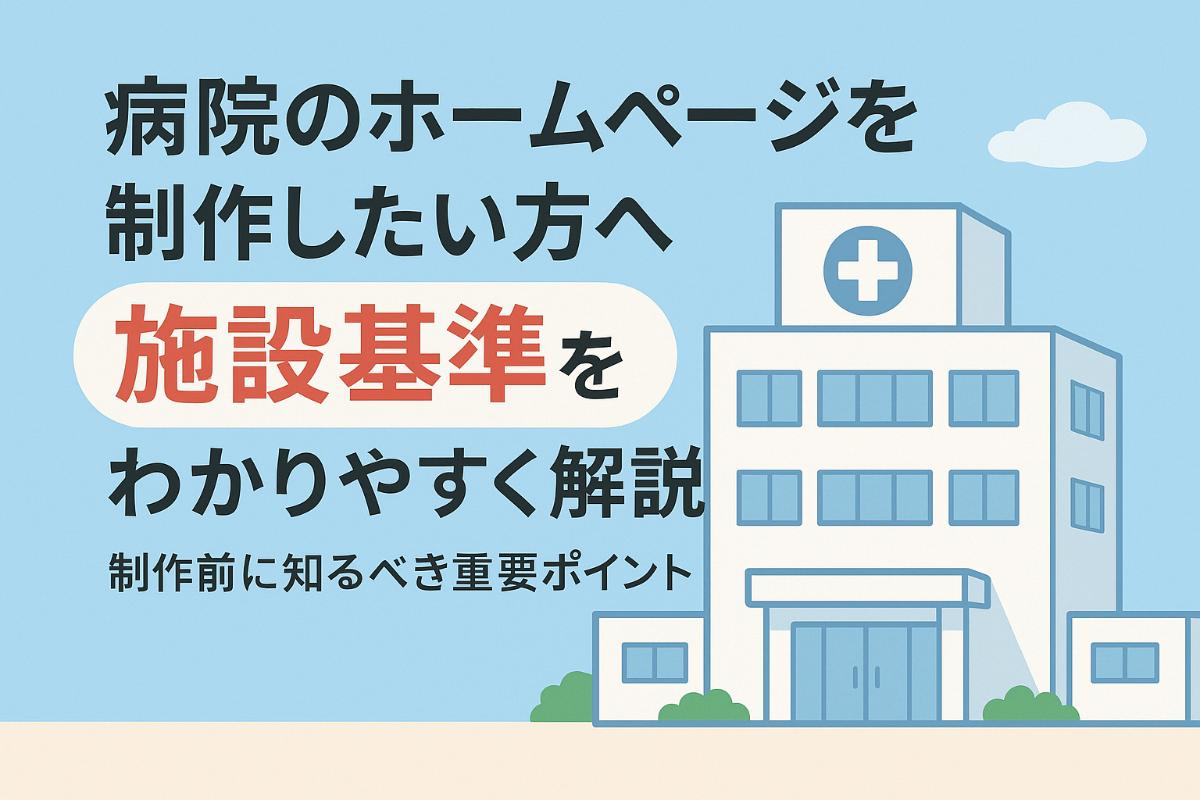
病院やクリニックの経営に直結する「施設基準」。診療報酬を算定するためには厚生労働省が定める基準を満たし、届け出を行う必要があります。しかし実際には「専門用語が難しくて理解できない」「ホームページに何を記載すればよいのか分からない」と悩む方も少なくありません。
例えば看護師配置基準やリハビリテーションの加算要件は、患者に安心感を与える大切な情報ですが、そのまま条文を載せても一般の人には伝わりにくいのが現状です。さらに現在の診療報酬改定では、施設基準に関する情報をホームページに掲載することが義務化され、適切に管理できていないと算定が認められないリスクもあります。
この記事では、病院施設基準をわかりやすく整理し、基本診療料から特掲診療料、看護体制や感染対策まで、患者に伝えるための表現方法を徹底解説します。最後まで読むことで「制度遵守と信頼性向上を両立するホームページの作り方」が理解でき、余計な費用や手戻りを防ぐ実践的なヒントも得られるでしょう。
医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgritsは、クリニックのホームページ制作を通じて集患をサポートします。患者様に選ばれるデザインと情報設計により、クリニックの魅力を最大限に引き出し、診療予約の増加を目指します。漫画や動画、SNS活用も取り入れ、オンラインでの集客力を高めます。各クリニックの特色に合わせたホームページ制作で、患者様との信頼関係を構築し、効果的な集患を実現します。

| 医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits | |
|---|---|
| 住所 | 〒550-0013大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F |
| 電話 | 06-4393-8493 |
病院における施設基準とは?ホームページ制作に必要な基礎知識
施設基準と診療報酬の関係をわかりやすく整理
病院やクリニックが診療報酬を算定するためには、厚生労働省が定める施設基準を満たし、各地方厚生局へ届け出を行う必要があります。施設基準とは、診療行為に加算をつけるための条件を示すルールであり、医療機関の体制や人員、設備、取り組みなどが対象になります。例えば、看護師の配置数やリハビリの体制、緩和ケアの実施環境など、具体的な基準を満たして初めて該当する加算を算定することができます。
診療報酬は、基本診療料と特掲診療料に大きく分かれます。基本診療料では初診料や入院基本料などが該当し、特掲診療料ではリハビリや在宅医療、検査や手術などが対象になります。施設基準を満たしていない場合、これらの加算は請求できません。つまり、施設基準は病院の経営に直結する極めて重要な要素といえます。
以下の表は、施設基準と診療報酬算定との関係を整理したものです。
| 分類 | 主な施設基準の例 | 診療報酬との関係 |
| 基本診療料 | 初診料、外来診療料、入院基本料 | 病院の基本収益に直結 |
| 特掲診療料 | リハビリテーション加算、在宅療養支援診療所加算 | 専門性や特色を示し収益を拡大 |
| 安全対策 | 医療安全管理加算、感染対策加算 | 患者の安心を担保し、信頼性を強化 |
| 看護体制 | 7対1、10対1などの看護配置基準 | 入院基本料の算定に必須 |
このように、施設基準は単なる制度ではなく、病院の収益構造を形成する重要な基盤です。基準を満たすことで診療報酬の幅が広がり、経営安定につながります。逆に、基準を満たせていない場合や届出が不備な場合には、算定ができず収益機会を失う可能性もあります。
加えて、施設基準は単なる数値要件ではなく、医療の質を示す指標でもあります。例えば「感染防止対策加算」を算定するためには、感染制御チームの設置や研修体制が必要であり、これは患者にとっても安心感につながる要素です。そのため、施設基準を正しく理解して対応することは、病院の信頼性やブランディングにも直結します。
この施設基準の内容を患者や地域住民へわかりやすく発信する場がホームページです。制度を正しく伝えることで、病院の姿勢や体制を理解してもらうことができ、信頼構築や集患効果につながります。単なる制度遵守のための内部管理にとどまらず、患者に選ばれる病院づくりの一環として、施設基準をどう見せるかが重要になります。
施設基準の届出とホームページ掲載義務(改定対応)
施設基準は、基準を満たしただけでは加算を算定することができません。正式に地方厚生局へ届出を行い、受理されて初めて算定可能となります。届出の際には、必要な様式に沿って書類を提出し、基準を満たしている証拠を揃える必要があります。人員配置表や勤務表、設備の写真や配置図など、書類の準備は多岐にわたります。
さらに、近年の診療報酬改定では、施設基準を満たしていることを患者に周知することが義務化されています。特に2024年の改定以降、施設基準に関する情報を病院のホームページに掲載することが求められるようになりました。つまり、病院の公式サイトで必要な情報を公開していなければ、算定が認められない場合もあるのです。
以下の表は、届出とホームページ掲載義務のポイントを整理したものです。
| 項目 | 届出の必要性 | ホームページ掲載の義務性 |
| 初診料関連の施設基準 | 届出必須 | ホームページに掲載必須 |
| 看護配置基準 | 届出必須 | 掲載推奨(患者への安心感向上) |
| 感染防止対策加算 | 届出必須 | 掲載必須(改定で義務化) |
| リハビリ加算 | 届出必須 | 掲載推奨(わかりやすく整理することで信頼性UP) |
届出の際に注意すべき点は、地域ごとに窓口となる地方厚生局の提出方法や締切が異なることです。電子申請に対応している場合もあれば、紙媒体での提出が求められる場合もあります。また、届出後も適時調査が実施され、要件を満たしていないと判断されれば返還を求められるリスクがあります。したがって、届出は一度きりではなく継続的な管理が必要です。
ホームページ掲載義務に対応するには、専門的な制度の内容を一般患者にもわかりやすく表現する工夫が不可欠です。難解な条文をそのまま載せるのではなく、平易な言葉や図表を用いて説明し、必要に応じてチェックリスト形式で整理することが効果的です。また、掲載内容は改定のたびに見直す必要があるため、制作段階から更新しやすい設計にすることも重要です。
ホームページ制作を依頼する際には、この施設基準の掲載対応を任せられるかどうかが制作会社選びのポイントとなります。制度改定の情報に敏感で、迅速に更新対応できる体制を持つ制作会社を選ぶことで、リスクを最小限に抑えられます。さらに、SEOの観点からも「施設基準」というワードを適切に配置することで、制度情報を探す患者や求職者に対して信頼性の高い情報発信が可能になります。
このように、施設基準の届出とホームページ掲載義務は、診療報酬を算定するためだけでなく、病院の信頼性を守り、患者に選ばれるための重要な要素です。届出の正確性とホームページでの表現力を両立させることが、クリニックや病院の経営に直結する課題といえるでしょう。
看護師配置基準やリハビリ施設基準をHPでどう表現するか
看護師配置基準(7対1・10対1)を患者に伝えるための表現方法
看護師配置基準は診療報酬の算定における大きな要件であり、病院の体制を示す重要な指標です。しかし「7対1」「10対1」という専門用語は、患者やその家族にとっては意味が分かりにくい数字表現になりがちです。ホームページで表現する際には、専門用語をかみ砕き、患者目線で安心感を持って理解できる形に変換する工夫が欠かせません。
例えば「看護師配置7対1」とは「患者7名につき看護師1名が常時配置されている」ことを意味します。これをそのまま数字だけで記載すると冷たい印象を与える可能性があります。そこで、以下のような言い換えを行うとわかりやすく伝わります。
| 制度用語 | 患者向け表現の例 | ホームページ掲載の工夫 |
| 看護師配置7対1 | 入院患者7名につき1名の看護師が常に担当しています | 「きめ細かなケアを提供できる体制を整えています」と補足 |
| 看護師配置10対1 | 入院患者10名につき1名の看護師が配置されています | 「患者様一人ひとりを丁寧にサポートしています」と柔らかく表現 |
| 夜間体制 | 夜間も複数の看護師が常駐しています | 写真やイラストで安心感を強調 |
このように表現すると、専門用語を知らない患者でも「人数が多いほど看護師が手厚い」というイメージを持ちやすくなります。特に高齢者や家族は「夜間や緊急時に対応してもらえるか」を重視するため、配置基準を伝えることは不安解消につながります。
また、ホームページ制作の観点からは、配置基準の情報を「診療案内」や「入院案内」ページに自然に盛り込み、写真やスタッフ紹介と合わせて提示することが効果的です。制度を遵守していることを示すだけでなく、患者の生活に直結するケア体制を表現することで、信頼性と集患効果を高められます。SEO対策としても「看護師配置基準」というキーワードを含めつつ、患者に寄り添った言葉にすることで、検索エンジンとユーザー双方に評価されやすい記事になります。
専門用語を避けて安心感を訴求する文章作成のコツ
施設基準は法的根拠のある制度であるため、通知文書や告示はどうしても難解な専門用語で書かれています。そのままの表現をホームページに掲載しても、患者や家族には理解されにくく、むしろ不安を与えてしまう場合があります。そのため、専門用語をできる限り避け、平易な表現に置き換えることが文章作成の大前提となります。
例えば以下のような言い換えが効果的です。
| 専門用語 | わかりやすい表現例 |
| 看護師配置基準7対1 | 「患者7名につき看護師1名が担当し、安心のサポートを行います」 |
| 疾患別リハビリテーション | 「症状に合わせた専門的なリハビリを提供しています」 |
| 感染防止対策加算 | 「院内感染を防ぐための徹底した安全対策を行っています」 |
文章の工夫としては以下のポイントが挙げられます。
- 難しい言葉を避け、誰でも理解できる表現に置き換える
- 専門的な制度の裏にある「患者の利益」を強調する
- 抽象的な数値だけでなく具体的なメリットを提示する
- 写真や図解を併用して視覚的に理解を助ける
例えば「当院は看護師配置基準7対1を満たしています」と書くのではなく「患者7名につき1名の看護師が担当し、きめ細かなケアを行います」と表現することで、患者は安心感を持ちやすくなります。同様に「疾患別リハビリを提供」とするよりも「脳卒中後の方には脳血管リハビリ、心臓病の方には心臓リハビリをご用意しています」と書くことで、自分に合った治療が受けられると理解できます。
ホームページ制作を依頼する際には、この文章作成の方針を制作会社に明確に伝え、専門用語に偏らない柔らかい文章を提案してもらうことが大切です。SEOの観点からは「看護師配置基準」「リハビリ施設基準」などのキーワードを自然に組み込みつつ、読者に安心を与える文章構成を作り上げることが検索順位上昇にも直結します。
施設基準掲載に強いホームページ制作会社を選ぶチェックポイント
医療専門の制作実績があるか
施設基準を正しくホームページに掲載するためには、一般的なWeb制作の知識だけでは不十分です。医療機関特有の制度や診療報酬に関する知識を持ち、実際に医療専門サイトの制作経験が豊富な会社を選ぶことが重要です。特に施設基準掲載は法令や厚生労働省の通知に基づくものであり、誤った表記や不正確な説明は患者の誤解を招くだけでなく、病院の信頼を損なうリスクにつながります。そのため、医療業界に特化した実績がある制作会社かどうかを必ず確認する必要があります。
医療専門の制作実績を確認する際のポイントを以下に整理します。
| 確認項目 | 注目すべき点 | 選定の基準となる質問例 |
| 制作実績の数 | 医科・歯科・薬局など幅広い分野の実績があるか | 「これまでにどの診療科のホームページを制作しましたか」 |
| 制作事例の公開 | 実際の制作事例をポートフォリオで確認できるか | 「公開されている医療機関のサイト事例を見せてください」 |
| 法令対応経験 | 医療広告ガイドライン、施設基準掲載義務への対応経験があるか | 「施設基準掲載や医療広告規制に対応した経験はありますか」 |
| クライアント層 | 開業医から大規模病院まで幅広い対応実績があるか | 「病院だけでなくクリニックや歯科にも対応可能ですか」 |
このように具体的な質問を通じて制作会社の実力を見極めることができます。医療に特化していない一般的な制作会社に依頼すると、制度理解不足により施設基準掲載が不十分になったり、患者目線に沿わない難解な表現がそのまま掲載されたりする恐れがあります。反対に医療専門の制作会社であれば、制度を遵守した上で患者が安心できる表現に翻訳し、デザインとSEOの両面で高い完成度を実現してくれます。
診療報酬改定や厚労省通知に対応できるか
施設基準は一度掲載すれば終わりではなく、診療報酬改定や厚生労働省からの通知に応じて定期的に更新が必要です。改定ごとに新しい基準が設けられたり、既存の要件が見直されたりするため、情報が古いまま残っていると制度違反のリスクや患者への誤情報につながります。そのため、制作会社が制度改定や厚労省通知に迅速に対応できるかどうかは非常に重要なチェックポイントです。
以下の表は、制作会社に求められる対応力を整理したものです。
| 項目 | 求められる対応 | 制作会社に確認すべき質問 |
| 診療報酬改定対応 | 改定内容を把握し、ホームページの文言や構成を修正できる | 「改定があった場合、どれくらいの期間で反映可能ですか」 |
| 厚労省通知の解釈 | 制度改正の通知や疑義解釈を理解し、正確に反映できる | 「通知に基づく掲載変更の実績はありますか」 |
| 更新体制 | 制作後も運用・保守を継続的に行う仕組みがある | 「制作後も改定対応を任せられますか」 |
| 費用の透明性 | 更新作業の費用体系が明確である | 「改定対応時の料金体系はどのようになっていますか」 |
制作会社が改定情報を常にウォッチしており、依頼者に代わって迅速に修正を行える体制を整えているかどうかを確認することが大切です。特に診療報酬改定は2年ごとに行われ、その間にも通知や疑義解釈が発出されるため、柔軟に対応できるパートナーであるかを慎重に見極める必要があります。単にホームページを作るだけでなく「制度の変化に追随できる更新力」がある会社を選ぶことが、長期的に安心して運用するためのポイントです。
SEO・MEOなど集患ノウハウを持っているか
施設基準を正しく掲載することは制度上の必須要件ですが、それだけではホームページが集患につながるとは限りません。患者に検索で見つけてもらい、安心して受診先に選んでもらうためには、SEO(検索エンジン最適化)やMEO(マップエンジン最適化)のノウハウが不可欠です。制作会社がこれらの知見を持ち、施設基準の掲載と同時に集患効果を高める施策を提案できるかを確認することが必要です。
SEOとMEOの観点から、制作会社に求めるべき要件は次の通りです。
| 分野 | 求められる知見 | ホームページへの反映例 |
| SEO | キーワード設計、内部リンク構造、コンテンツ最適化 | 「施設基準」「看護師配置基準」など制度関連キーワードを自然に配置 |
| MEO | Googleビジネスプロフィール最適化、口コミ対策 | 地域名+診療科名での検索上位化、施設基準情報を地図情報に反映 |
| コンテンツ戦略 | FAQ、チェックリスト形式、患者目線の説明文 | 制度情報を図解やリスト化して読みやすさを強化 |
| データ活用 | アクセス解析、検索順位モニタリング | 検索流入の改善や弱点の特定を定期的にレポート |
単なる制度掲載に留まらず「検索で見つかりやすくする」「地域の患者が選びやすくする」という観点で提案できる制作会社は、病院やクリニックにとって大きな価値があります。SEOキーワードを適切に盛り込みつつ、患者に寄り添った自然な文章表現を実現できる会社であれば、制度遵守と集患効果を同時に満たすホームページを作り上げることができます。
施設基準掲載はあくまで制度上の義務ですが、それをどのように魅力的に見せ、患者に選ばれる病院づくりにつなげるかが制作会社の腕の見せどころです。SEO・MEOのノウハウを持つ会社を選ぶことで、制度対応を超えて経営戦略としてのホームページ活用が可能になります。
制作依頼を検討中のクリニックがやるべき準備リスト
施設基準届出書類を整理しておく
クリニックがホームページ制作を依頼する際、まず最初に取り組むべきことは施設基準の届出書類を整理することです。施設基準は診療報酬の算定に欠かせないものであり、厚生労働省や各地方厚生局に届け出を行うことが求められます。届出内容は診療報酬を算定する根拠であると同時に、患者に対して信頼を示す情報でもあります。そのため、ホームページに情報を掲載する場合は届出に基づく正確な内容を反映させることが重要です。
施設基準届出書類には、医師や看護師の勤務体制、病床数、リハビリ室の広さや設備、感染防止対策に関する取り組みなど、多岐にわたる情報が含まれます。制作会社に依頼する前に、以下のような書類を整理しておくことをおすすめします。
| 書類の種類 | 内容 | ホームページ掲載との関連性 |
| 施設基準届出書(様式) | 厚労省が指定する各種様式 | 施設基準の正式根拠として必須 |
| 勤務表・シフト表 | 看護師や医師の配置体制 | 看護師配置基準の掲載根拠 |
| 設備・機器リスト | リハビリ機器や医療機器の一覧 | 設備紹介ページや写真掲載に活用 |
| 研修実施記録 | 感染対策や医療安全に関する研修記録 | 安全性や信頼性を示す証拠 |
| 患者数・稼働実績 | 外来患者数や入院稼働率 | 診療体制の透明性を示す要素 |
これらを制作会社に渡すことで、制度的な正確性と患者に向けた分かりやすい説明を両立できます。整理が不十分だと掲載内容に誤りが生じ、施設基準に対応できないだけでなく、SEOにもマイナスの影響が出かねません。情報を正しく整理することが、制度遵守とホームページ品質の両立に直結します。
掲載必須項目・写真素材・データの準備
次に重要なのが、ホームページに掲載する必須項目や写真素材、各種データの準備です。施設基準の掲載は診療報酬算定のための義務だけでなく、患者に選ばれるための大切な情報発信でもあります。したがって、制作会社に渡す段階で整理された素材を準備することが効率的な制作につながります。特に、情報が不十分な状態で制作を進めると、修正や追加作業が頻発し、結果的に余計な費用や時間がかかる可能性があります。そのため、事前の準備は単に「効率化」の意味だけでなく、完成度の高いホームページを作るうえで欠かせないプロセスです。
必須項目の代表例は以下の通りです。
| 区分 | 掲載必須項目 | 患者にとっての意味 |
| 基本診療料 | 初診料、外来診療料、入院基本料 | 標準的な診療体制を理解できる |
| 特掲診療料 | リハビリ加算、緩和ケア加算、在宅医療加算 | 専門性や特色を示し差別化につながる |
| 感染防止・安全管理 | 医療安全加算、感染防止対策加算 | 安全性や安心感を患者に伝える |
また、これらを補足する写真素材やデータも不可欠です。リハビリ室の写真、スタッフの集合写真、感染対策の様子などは、患者が視覚的に安心感を得るために重要です。文章だけでは伝わりにくい部分をビジュアルで補うことで、信頼度と訴求力が高まります。さらに、写真やデータを豊富に揃えることで、検索エンジンからの評価も上がり、結果的にSEO効果の向上にもつながります。
制作会社に依頼する前に以下の準備を整えておくとスムーズです。
- 院内外の写真撮影(病棟、診療室、リハビリ室など)
- 看護師やスタッフ紹介写真
- 各種統計データ(年間外来患者数、平均入院日数など)
- 診療時間表やアクセスマップ
これらの素材を事前に整理することで、制作会社が即座にページ構成に反映でき、納期短縮やコスト削減につながります。さらに、整理された情報は「患者にとって知りたいことがすぐ見つかる」使いやすいサイト設計を実現し、結果としてクリニック全体の信頼性を高めることにつながります。
院長メッセージや理念と施設基準をリンクさせる
ホームページにおいて、制度情報を単に羅列するだけでは患者の心には響きません。制度的な基準を満たしていることはもちろん重要ですが、それを院長メッセージやクリニックの理念と結びつけることで、他院との差別化を図り、患者の共感を得ることができます。
例えば、看護師配置基準を単に「7対1を満たしています」と掲載するのではなく、「患者様一人ひとりに寄り添った医療を提供するために、厚生労働省が定める厳しい基準を満たし、看護師体制を整えています」と院長の言葉で伝えることで、安心感と誠実さを強調できます。これは制度をただ説明するだけでは生まれない付加価値です。
理念と施設基準を結びつける具体例を以下にまとめます。
| 項目 | 制度表現 | 患者に伝える表現例 |
| 看護師配置基準 | 7対1配置を満たしている | 「一人ひとりに丁寧に寄り添うために、看護師体制を充実させています」 |
| リハビリ施設基準 | 面積・スタッフ数基準を満たしている | 「快適な空間と専門スタッフで、安心して回復に専念できる環境を整えています」 |
| 感染防止対策加算 | 感染対策チームを設置 | 「患者様の安全を第一に考え、徹底した感染対策を実施しています」 |
こうした文章はSEO的にも効果的です。制度名称を自然に含みつつ、理念と結びつけることで、検索エンジンに評価される網羅性と、読者の共感を得られる柔らかさを両立できます。さらに、院長のメッセージを動画やインタビュー形式で掲載すれば、より一層信頼性が高まります。
このように、制度遵守と理念をつなげた発信は、単なる情報掲載を超えた「ブランド発信」となり、患者に選ばれるクリニックづくりにつながります。
まとめ
病院やクリニックにとって施設基準は、単なる制度要件ではなく診療報酬を算定するための生命線ともいえる存在です。例えば初診料や入院基本料といった基本診療料は経営の基盤を支える収益に直結し、リハビリや緩和ケアなどの特掲診療料は専門性を示す大きな武器になります。加えて、看護師配置基準や感染防止対策加算といった体制整備は、患者に安心感を与える信頼性の証でもあります。厚生労働省の告示では現時点でホームページへの掲載義務も定められており、正確な届け出と情報公開を怠れば算定そのものが認められないリスクもあります。
一方で、多くの院長や事務長が直面するのは「専門用語が難解でわかりにくい」「ホームページにどう記載すれば患者に伝わるのか不安」という悩みです。たとえば「看護師配置7対1」という表現をそのまま載せても一般の人には伝わりにくく、「患者7名につき1名の看護師が常に対応しています」と言い換えるだけで理解度と安心感が大きく変わります。こうした工夫こそが制度の正しい理解と患者への誠実な情報発信を両立させます。
この記事で整理した内容を実践すれば、施設基準の届出書類を整理し、必須項目や写真素材を事前に準備し、さらに院長メッセージや理念と結びつけた情報発信が可能になります。放置してしまえば「算定漏れによる収益損失」や「信頼低下」という大きな代償を招きかねませんが、正しく対応すれば患者から選ばれる医療機関へとつながります。
制度遵守と患者目線の表現を両立し、専門性と安心感を兼ね備えたホームページを構築すること。それが現在以降の医療機関に求められる新しい基準であり、経営安定と地域からの信頼を獲得する近道となるでしょう。
よくある質問
Q. 病院の施設基準をわかりやすく知りたいのですが、診療報酬にどのくらい影響がありますか
A. 施設基準を満たしていないと初診料や入院基本料が算定できず、病院の基本収益が減少する可能性があります。例えば看護師配置基準7対1を満たしている場合と10対1の場合では、1日あたりの入院基本料に数千円規模の差が生じるため、年間で換算すると数百万円単位の収益差につながります。つまり、施設基準は病院経営に直結する大きな要素であり、正しい届出とホームページでの明示が欠かせません。
Q. 施設基準の届出をしないままホームページに掲載しなかった場合、どのようなリスクがありますか
A. 厚生労働省の通知により、2024年以降は一部の施設基準でホームページへの掲載が義務化されています。届出をしていない、またはホームページで公開していない場合、算定が認められず返還を求められるリスクがあります。例えば感染防止対策加算は届出必須かつ掲載必須であり、未掲載だと加算が無効になるケースもあるため、クリニックや病院にとっては年間数十万円以上の損失につながりかねません。
Q. 看護師配置基準やリハビリ施設基準を患者に伝えるときに、どんな表現が効果的ですか
A. 専門用語を避けて、患者に安心感を与える表現に変換することが効果的です。例えば「看護師配置基準7対1」は「患者7名につき1名の看護師が常に担当」と説明すると理解しやすくなります。また「リハビリ室の面積が40平方メートル以上必要」という制度文言は「広々とした空間で安心してリハビリを受けられる」と言い換えると伝わりやすいです。このように制度の数値要件を具体的なメリットに置き換えることが、集患と信頼構築の両方に直結します。
Q. クリニックがホームページ制作を依頼する際、施設基準の準備はどの程度必要ですか
A. 制作依頼前に届出書類や必須項目を整理しておくことが重要です。例えば勤務表やシフト表、設備リスト、研修実施記録を事前にまとめておくと制作がスムーズに進みます。さらに、初診料やリハビリ加算、感染防止対策加算など掲載必須項目を揃えておくことで、修正作業や追加コストを回避できます。整理が不十分な場合、制作後に何度も修正が必要となり、結果的に数十万円規模の余計な費用や納期遅延につながることもあるため、事前準備が成功の鍵となります。
医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgritsは、クリニックのホームページ制作を通じて集患をサポートします。患者様に選ばれるデザインと情報設計により、クリニックの魅力を最大限に引き出し、診療予約の増加を目指します。漫画や動画、SNS活用も取り入れ、オンラインでの集客力を高めます。各クリニックの特色に合わせたホームページ制作で、患者様との信頼関係を構築し、効果的な集患を実現します。

| 医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits | |
|---|---|
| 住所 | 〒550-0013大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F |
| 電話 | 06-4393-8493 |
会社概要
会社名・・・医科・歯科専門HP制作会社|Medicalgrits
所在地・・・〒550-0013 大阪府大阪市西区新町1-3-12 四ツ橋セントラルビル9F
電話番号・・・06-4393-8493
